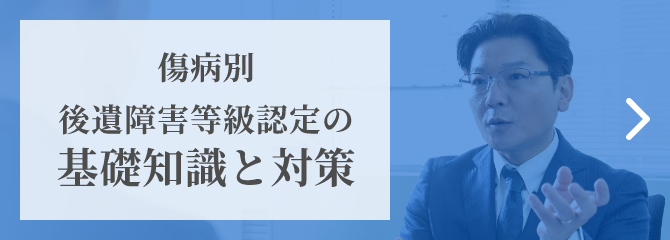後遺障害認定
交通事故で使える社会保障制度について~2労災保険
当事務所では、交通事故で労災を使うべきであると判断しています。
業務中や通常の通勤経路上での通・退勤時の交通事故では、労災保険の適用対象になりますが、相手方任意保険会社が自賠責一括対応をしている場合、いまだに「勤務先から労災を使う意味はないといわれた」、「労災を使ったら損」など誤解して労災を使わない方がおられます。
また、WEB上でも誤った情報や誤解を招きかねない記載がまだまだ散見され、賠償実務上混乱が見られます。
もちろん、勤務先との関係を考慮し、敢えて労災を使わないという判断をされるのであればいいのですが、当事務所では労災事案の場合、労災を使うべきことを推奨しておりますので、今一度、交通事故で労災を使うメリットについて説明します。
なお、労災事案では、労災を使っているか否かを問わず、健康保険が利用できません(健康保険法55条1項)。
労災事案で健康保険を使用していることが役所や健保協会・組合に判明した場合、保険給付額の返還を求められますので十分注意してください。
また、相手方保険会社やご自身の人身傷害保険の担当者から健康保険の使用を勧められた場合、担当者の理解が不十分であったり労災事案であることを把握していない場合もありますので、必ず労災事案であることを説明してください。
1 治療費打切りの恐れが少ない
任意保険会社は営利民間企業ですし、そもそも治療中の治療費の支払いは保険会社のサービスにすぎないことなどから、まだ治療の必要性や相当性が認められるにもかかわらず、相手方任意保険会社からの治療費の支払い(内払い)が早期に打ち切られてしまうことがあります。
これに対し、社会保障制度である労災保険では、むやみに治療費の支払いを打ち切ることなく、治療の必要性と相当性が認められる限り、比較的長期間治療が認められます。
なお、冒頭に述べたとおり労災事案では健康保険が使用できませんので、まだ治療が必要であるにもかかわらず、相手方任意保険会社からの治療費の支払いが打ち切られた場合、健康保険に切り替えて通院を継続することができません。
その場合、自由診療での治療費を自己負担することは現実的ではありませんので、労災に切り替えることが必要になりますが、その時点で労災申請を行い、療養給付を受けるためには時間がかかり診療機関に迷惑が掛かりますし、その間、治療費の自己負担を求められることもあります。
相手方保険会社からの治療費打切り後の通院のことも考えると、当初から労災を使っておいた方が余計な混乱を防ぐことができます。
なお、労災事案でも症状固定後については、慢性疾患に対する治療として健康保険の使用が認められる場合があります。
2 被害者に過失が認められる場合治療費の自己負担分が抑制でき、重過失による支給制限が行われないこともある
被害者にも過失が認められる場合、被害者の損害のうち過失割合に相当する部分は自己負担しなければなりません。
そして、治療費については、診療報酬制度により診療点数で定められ、労災では1点あたり12円とされることが一般的ですが、相手方任意保険による一括対応の場合は、自由診療として1点当たり20円とされます(これ以上の報酬を請求する医療機関もあります)。
すなわち、労災を使用することで同じ治療を受けても、自己の過失割合に相当する自己負担額を4割(自由診療20円の場合)減額することができます。
例えば、被害者側過失割合20%、診療報酬1万点の場合
自由診療 自己負担額 1万点×20円×0.2=4万円
労災 自己負担額 1万点×12円×0.2=2万4000円
また、被害者に70%以上の過失が認められる場合(故意及び100%過失であれば、自賠責も労災も支払われません)、自賠責では傷害部分につき2割減額、後遺障害部分については段階的に2乃至5割減額されますが、労災でも休業・障害給付の3割の支給制限規定は設けられているものの(労働者災害補償保険法12条の2の2・昭和40.7.31基発第906号、昭和52.3.30基発第192号)、労災では実務的にはさほど重過失による支給制限は行われていない印象があります。
そのため、被害者側にも過失が認められる場合、労災を使うメリットは大きいといえます。
3 特別支給金の支払いが受けられる
労災には本体部分(療養・休業・障害補償等)の給付のほか、休業給付及び障害給付等では特別支給金が支払われます。
本体部分の給付については、損益相殺・受給調整の対象(支払われた分は他から同一の給付・支払を受けらないこと)となり二重払いを受けることができませんが、特別支給金は損益相殺の対象となりません。
つまり、労災を使えば、特別支給部分はもらい得になります。
例えば、休業(補償)給付では、事故直前3か月間の給与支給額を歴日数割した給付基礎日額の6割の本体部分に加え、2割の特別支給金が支払われます。
そして、労災で支払われなかった本体部分の残り4割部分を相手方任意保険会社から支払いを受ければ、計12割の休業損害が支払われることになります。
また、労災でも自賠責と同様の基準で後遺障害認定を受けられますが、等級認定を受けた場合、本体部分の障害年金/一時金のほか、342万円(1級)~8万円(14級)の障害特別支給金のほか、障害特別年金/一時金の支給が受けられます。
12割の休業(補償)給付を受けるためには
ここで、特別支給部分を含めた12割の休業給付金を得るための方法を説明します。
(1) 休業扱いにすること
まず、労災の場合有給休暇を使用した場合は、休業給付の対象となりません(自賠責や任意保険会社は有給も休業損害の対象です)ので、有給は使わず給与の支払いを伴わない休業扱いにしてもらうことが必要です。
(2) 必ず労災から請求すること
相手方保険会社から当該休業月につき、100%の休業損害が支払われる場合は、労災に20%の特別支給金だけを請求すればいいので、特に問題は生じませんが、相手方保険会社から100%の休業損害が支払われない場合に問題が生じます。
つまり、労災から当該休業月の休業給付金の支給を受ける前に、相手方任意保険会社から給付基礎日額の6割を超える休業損害の支払いを既に受けた場合は、当該休業月については、労災から本体部分の支払いは受けられなくなります(特別支給金の支払いは受けられます)。
例えば、事案を単純化し、月収30万円の方が当該休業月につき、相手方任意保険会社から20万円の休業損害の内払いを受けた場合、20万円は受給調整の対象となるので(30万円×0.6-20万円<0円)、労災から追加で10万円の休業給付は受けられず、6万円の特別支給金のみ支払われます(相手方任意保険会社から10万円の支払いを受けた場合は、労災から8万円の本体部分(30万×0.6-10万円=8万円)と6万円の特別支給金が支払われます)。
上記の労災の受給調整に該当しないようにするためには、まず当該月の休業給付を労災に請求します。
上記の例でいえば、18万円の本体部分と6万円の特別支給金の計24万円が労災から支払われます。
その後、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい労災支給決定通知と併せ、相手方任意保険会社に送付し残りの4割の休業損害を請求すれば良いのです。
上記の例でいえば、相手方任意保険会社からさらに12万円の休業損害が支払われ、これで当該月の休業給付/損害は合計36万円となります。
(3) 労災の待機期間3日分は有休扱いにして、相手方任意保険会社に請求すること
労災の休業給付は、労災により賃金を受けない日の4日目から請求でき、当初の3日分の休業分は労災から支給が受けられません(待機期間)。
この間は、特別支給金も支払われませんが、有休休暇を取得すれば、相手方保険会社からは有休消化分の3日分の10割の休業損害の支払いが受けられます。
なお、待機期間中は有休扱いにしなくても、勤務先から6割の休業補償が受けられます(労働基準法76条)。
(4) 休業日から2年以内に労災請求をすること
労災の休業給付は2年の消滅時効にかかるので、休業日から2年以内に労災請求をしてください。
なお、相手方保険会社から休業損害の支払いを受けていても、2年以内であれば特別支給金の支払いは受けられるので、請求することを忘れないようにしてください。
4 労災で後遺障害認定を受けることができる
自賠責での後遺障害認定基準(自賠法施行令別表Ⅰ・Ⅱ)が、労働者災害補償保険法施行規則別表Ⅰに準じて定められたとおり、自賠責と労災では同一の後遺障害認定基準が用いられています。
しかし、例えば、運用上労災では脳脊髄液漏出症が後遺障害の対象となる一方で、自賠責では事実上認められなかったり、高次脳機能障害の具体的認定基準が異なるなど、社会保障制度である労災保険の方がより後遺障害認定が認められやすい傾向にあります(一方で、上・下肢の醜状痕における「露出面」の解釈などでは、自賠責の方が対象が広いこともあります)。
また、認定手続上も、自賠責での後遺障害認定は、損害保険料率算出機構で原則書面審査により組織的に判断されるのに対し、労災では全件労災医と面談したうえで、労災医の意見にしたがって認定される点で、労災医の意見によってはより後遺障害が認められやすい傾向にあります。
そして、労災で後遺障害認定が受けられれば、自賠責等との需給調整の対象となりますが障害年金(1級~7級)や障害一時金(8級~14級)が受けられるほか、先に述べたもらい得の特別支給金の支払いが受けられます。
さらに、良く見逃されがちですが、勤務先によっては、福利厚生の一環として労災で後遺障害認定を受けた場合、労災給付とは別に一定の給付金が支払われる制度を設けている場合もあります。
なお、労災の後遺障害申請をする場合、主治医の先生に労災書式の診断書を記載いただくことが必要ですので、主治医の先生に二度手間をおかけすることを避けるため、自賠責の後遺障害診断書と併せ労災書式の診断書を同時に記載いただくと良いでしょう。
自賠責と労災の後遺障害認定が異なった場合は?
上記のとおり、労災と自賠責では認定基準は同一ですが、運用上・手続上の違いにより認定等級が異なることが多々見られますが、相手方任意保険会社は、自賠責の等級認定基準のみにしたがいます。
つまり、相手方任意保険会社は、自賠責で14級にもかかわらず労災で12級の認定が得られたからといって、12級前提での保険金の支払いには応じませんし、自賠責での等級認定にしたがい14級前提で示談がされた場合、後に労災で12級が認定されたからといって、追加で12級前提での保険金を支払うことはありません(訴訟をしても示談済ですので請求棄却されますし、錯誤無効を主張することも困難です)。
また、大変残念ながら、訴訟の場においても裁判所は自賠責の等級認定に事実上大きく影響されますが、自賠責の認定等級以上の等級を前提に訴訟をしようとする際には、労災で当該等級の認定を受けていることは一つの証拠になります。
すなわち、労災での認定等級が自賠責の等級を上回る可能性があるので、自賠責での異議申立てや紛争処理申請での自賠責の認定等級の見直しや、訴訟での上位等級認定の可能性を見極めるため、労災の等級認定を俟たず自賠責での認定等級を前提とした示談は控えるべきで、自賠責と労災の双方の認定結果を検討したうえで、相手方任意保険会社と示談するか、異議申立てや訴訟を提起するか検討することが望ましいと考えます。
勤務先が労災の適用を拒否する場合の対応について
業務中もしくは通・退勤時の事故であり、労災が適用される場合であっても、勤務先が労災の申請を拒否する場合が大変良くみられます。
そもそも、交通事故で労災を使うかは被害者の自由判断に委ねられます。
ただ、労災の申請には、勤務先の証明や平均賃金の算定、資料の提出などで勤務先の協力が不可欠です。
勤務先が労災申請を拒否する理由として、「相手方任意保険会社が対応しているから、労災を使う意味がない。」と言われることが多いのですが、上記のとおり、交通事故で労災を使うメリットは大きいにもかかわらず、勤務先担当者がまだまだ誤解していることが多くみられるので、その場合は、上記のメリットを挙げて労災の申請に協力してもらことが必要です。
また、労災を使うと労災保険料の事業所負担額が上がるということも理由として考えられます。
確かに業務災害の場合、常時100人以上の労働者を使用する会社や、常時20人以上の労働者を使用する会社であり労働災害が多い災害度係数が0.4以上の会社では労災保険料が上がる場合がありますが、通勤災害の場合労災保険料の値上がりはありません。
そこで、通・退勤時の交通事故の場合や、業務災害であっても上記事業所に該当せず、労災保険料の値上がりはないことを勤務先に説明して申請に協力してもらいましょう。
それでも、勤務先が労災の申請に応じない場合、勤務先所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
なお、労災の申請書は、厚労省のHPからダウンロードでき、ご自身で作成し、所轄の労働基準監督署に申請することも可能です。
後遺障害認定
- 高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
- 高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
- 東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
- 右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
- 右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
- 上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について
- 自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について
- むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
- 右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと
- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
-
高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
-
東京海上日動火災保険㈱の不相当な治療費打切り理由について
-
韓国旅行中に交通事故に遭ったら
-
令和7年11月3日 韓国光州弁護士会・愛知県弁護士会共同セミナー講師を務めました。
-
東海交通遺児を励ます会の会報「はばたけ」100号記念号が発刊されました。
-
東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
-
右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
-
右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
-
三井住友海上火災の車両時価額の算定方法について~中古車販売価格の地域差を考慮に入れるべきでしょうか