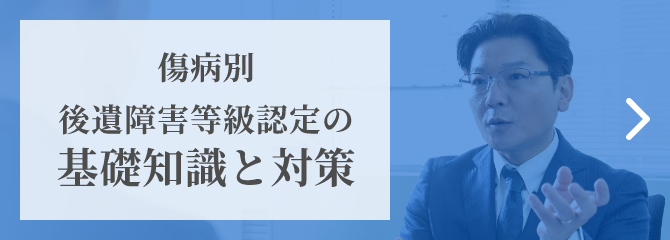傷病別後遺障害等級認定の基礎知識と対策
傷病別後遺障害等級認定の基礎知識と対策
靭帯・腱等損傷
靭帯とは骨と骨を結び付けている結合組織であり、腱とは骨格筋と骨を結び付けている結合組織をいいます。交通事故により、肩・肘・股関節・膝・手足等の関節部を骨折・脱臼・捻挫・打撲等をした場合、各部位によって以下の靭帯等の軟部組織を損傷する可能性があります。
靭帯・筋腱類は、関節の可動を掌る重要な組織であり、これらを断裂・損傷すると関節可動域の制限・痛みなどの後遺障害が生じます。
なお、関節可動域制限での後遺障害認定の基礎知識については、こちらをご覧ください。
肩:腱板・関節唇
肘:内外側側副靭帯
手関節:三角線維軟骨複合体(TFCC)・掌背側・側副靭帯等
股関節:関節包靭帯
膝:前後十字・内外側側副靭帯・半月板
足関節:足内側靭帯:三角靭帯(前脛距靭帯、脛舟靭帯、脛距靭帯)
足外側靭帯:前距腓靭帯・踵腓靭帯、後距腓靭帯
靭帯・筋腱類の損傷により、上記関節の可動域制限が生じた場合、後遺障害等級は、
肩・肘・手関節であれば、「1上肢の三大関節の機能障害」
股・膝・足関節であれば、「1下肢の三大関節の機能障害」
として、
1つの関節の可動域が10%程度以下に制限: 1関節の用を廃として8級
1つの関節の可動域が2分の1以下に制限 : 1関節の機能に著しい障害を残すものとして10級
1つの関節の可動域が4分の3以下に制限 : 1関節の機能に障害を残すものとして12級
その他、用を廃した関節の数などによって1級から6級に該当し、また、前腕の回内・回外障害が生じた場合、動揺関節が生じた場合、習慣性脱臼が生じた場合も、上肢・下肢の機能障害として後遺障害の対象となります。
しかし、12級以上の後遺障害の認定を受けるためには、これら靭帯・筋腱類の損傷が画像上捉えられていることが必要です。また、これらの損傷を画像上捉えることが困難であっても、受傷態様や各種検査結果により損傷が明らかな場合、12級以上の認定を受けることができる場合もあります。
腱板損傷における外傷損傷と慢性症状の区別について
事故後、「腱板」と呼ばれる肩関節を構成する筋腱類(棘上・棘下筋腱、小円筋腱、肩甲下筋腱)を損傷することがあります。これは、肩を直接打撲した場合のみならず、停車中ハンドルを握っている際に追突を受け、肩に急激かつ大きな力が加わった場合などにも生じます。
しかし、最近の疫学調査において、肩への外傷がなくても、50歳代で10人に1人、80歳代では3人に1人の割合で腱板損傷が生じており、そのうち無症候性(自覚症状がないもの)の損傷が半分以上を占めることが明らかになりました。
また、肩を酷使するスポーツ歴や職歴のある方にも腱板損傷がみられる場合があります。
そのため、事故後腱板損傷が明らかになった場合、これらの慢性化・陳旧化した腱板損傷か、事故による外傷で生じた腱板損傷かが問題になることが近時多発しています。
事故当初から早期にMRIを撮影していれば、損傷した腱板部周辺に血腫や水腫、骨挫傷像が得られるなどの新鮮外傷と思われる所見が得られることがありますが、事故後数か月経過してから初めてMRIが撮影された場合などでは、陳旧化した損傷か外傷損傷か区別ができなくなります。
その場合であっても、慢性化した腱板損傷では、長期間の腱板の変性に伴い、上腕骨頭と肩峰間の関節裂隙が狭小化していたり、骨の関節面での変形である骨棘の形成や軟骨下骨部分の骨硬化など、いわゆる変形性関節症と同様の変化を示していたり、周辺筋肉の萎縮が生じている場合があります。
これら変化は腱板損傷後長期間を経て形成されますので、腱板損傷があるにもかかわらず、これら変形性関節症性変化を示していない場合、事故による外傷性の腱板損傷であるといえる可能性が高まります。
外傷性と陳旧性変化との鑑別に必要な検査については、下記「対策」の2で詳述しています。
無症候性の慢性腱板損傷が事故により症状を呈したとして14等級を認めた事例(千葉地裁平成29年6月28日判決)
万が一、腱板損傷が事故により生じたものではないとしても、事故前は症状がなく事故により発症したとして後遺障害等級14級を認めた判例(千葉地裁平成29年6月28日判決・自保ジャ2006・55)が出ましたので、その判旨を抜粋します。
「(医師2名の)意見は、いずれも、本件事故により新鮮性の腱板断裂が発症したことについては否定的であり、〇医師は腱板断裂が本件事故以前よりあった可能性が高いとし、〇医師も腱板断裂が元々存在していたと考えることが自然であるとする。
そして、腱板断裂が50歳以上の中高年でよく起こるが、年齢が上がるほど、外傷歴を自覚しないか、外傷なく発症する割合が増え、必ずしも症状を発する病態であるとは限らないところ、〇医師の意見のとおり、このような無症候性の腱板断裂がある場合に、頚椎捻挫等による頚部肩甲帯周囲の筋緊張が亢進があれば、肩胸郭機能不全、肩甲骨可動域低下により、腱板断裂が有症候性に変わることは、経過として不自然ではなく、原告が本件事故後1か月後に肩の症状を訴えるに至ったことも、このような観点から十分説明することができる。
ただし、本判例は下記のとおり述べ、既往症減額を25%認めました。
「無症候性の腱板断裂が高齢者に多いものの、これが平均的な65歳の者の身体的特徴の範囲内ということができるかについては疑義があり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用するのが相当である。もっとも、腱板断裂が疾病であるとしても、無症候性であり、高齢者に多いことは、素因減額により減ずる割合を少なくする方向で斟酌すべきである。」
対策
1 早期の症状の訴え
早期の症状の訴えは最も重要で、その有無については自賠責の後遺障害認定の際や訴訟で争いになることが極めて多くみられます。
一般に、後遺障害の原因となるような重い靭帯・腱等の軟部組織の損傷を伴う場合、受傷当初から受傷部位の激しい痛みを伴うとされます。
そのため、受傷当初から当該部位の痛み等の症状が訴えられていない場合(訴えたとしても、診断書やカルテ等に記載がない場合)、後に撮影されたMRIやエコー画像上靭帯・腱等の損傷が生じていたとしても、事故と無関係とされこれら損傷と事故との因果関係が否定される恐れがあります。
受傷当初はその他の打撲や擦過部の痛みが強く、肩や膝等の軟部組織の損傷があった部位の痛みが隠され、これらの症状が落ち着いてきた際に肩や膝等の症状が徐々に自覚されてくることや、受傷直後は身体が興奮状態にあり痛みを感じにくい状態にあったりすることはよく見られ、また、受傷当初は混乱状態にありすべての症状を医師に的確に伝え、医師がこれらの症状をすべて記録化してくれているとは限りません(受傷当初の訴えの問題点は、こちらを参照ください)。
さらには、頚・腰椎捻挫を伴うような受傷態様の場合、肩や膝などの関節部を単独受傷し、痛みを訴えたとしても、医師は「頚/腰からくる症状」と診断して、当該部位の診断名を付してくれないこともあります。
ただし、上記の点については自賠責調査事務所や裁判官は理解してくれません。
そのため、症状が生じていることに気付いたら、医師にできる限り早期に症状を訴え、記録化してもらうことが極めて大切です。
2 早期のMRI撮影・エコー検査の実施
靭帯・筋腱類はレントゲンやCT画像では捉えられず、MRI画像やエコー画像により捉えられます。ところが、関節組織は極めて複雑ですので、より精度の高いMRI装置でないと、画像が荒く見落とされることもあり、また撮影角度によってもこれらの損傷を捉えきれないこともあります。
また、画像上靭帯・筋腱類の損傷が明らかになったとしても、事故から時間が経過してしまうと、軟部組織の損傷が見つかっても、事故によるものか、もともと生じていた慢性化した陳旧性の病変か区別がつかなくなってしまうことも多々見られます。
交通事故による靭帯・筋腱類の損傷が生じた場合、早期のMRI画像では血腫・水腫等の周辺組織の炎症性変化や骨挫傷像が得られることが一般的ですが、これらの画像上の変化は時の経過ともに消失するので、事故から相当期間が経過した時点で撮影されたMRI画像では、これらの軟部組織の損傷が事故によるか元々あった加齢性変化等と区別がつかなくなります。
そのため、できる限り当該部位のMRI撮影をしていただくことがとても重要です。
また、肩・肘・手首等の上肢は頚を受傷したことに伴う症状であるとか、膝や足首などの下肢は腰を受傷したことに伴う症状だとして、これらの関節を単独で損傷したことが見逃されることが非常に多くみられます。
これらの関節部位に対し、直接車両が衝突したり、アスファルト路面上に叩き付けられたリした場合は、比較的わかりやすいのですが、乗車中であってもハンドルを握っている手の肩に強い衝撃が加わったり、ダッシュボードなどに膝を強くぶつけたり、事故の衝撃を耐えるため強く足を踏ん張ったため膝に強い力が加わった場合などでも、肩や膝関節の筋腱類等を損傷する場合もあります。
そこで、交通事故により上下肢の関節及び関節付近を受傷し、痛みや関節可動域の制限が生じた場合、その旨を主治医の先生にお伝えし、できる限り早期に精度の高いMRI装置により、多面的な角度で画像を撮影していただいたり、エコー画像で軟部組織の損傷がないか確認していただくことが大切です。
その他、外傷性を裏付ける他覚的な検査として、関節鏡検査によれば直接軟部組織の状態目視できます。
また、外傷による関節軟部組織の損傷の場合、関節液内の血液成分の混入が認められる場合がありますし、関節液内に脂肪滴が見られれば骨折している可能性がありますので、間接穿刺による関節液検査も有用です。
3 関節可動域の正確な検査
可能であれば、受傷直後から経時的に受傷した関節及び健側の可動域の検査を行っていただいて下さい。
稀に誤った測定方法や記載方法をされる先生もいますので、必ず、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会によって決定された「関節可動域表示ならびに測定方法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」に定められた方法により測定していただいてください。
また、関節可動域の数値により後遺障害等級が定まりますので、できるだけ正確に測定していただいて下さい。
なお、医師から「肩動く?」と聞かれて、一応動くので「動きます。」と答えたことで、診断書やカルテ等に「可動域制限なし」と記載されてしまうこともあるので、受傷した関節の動きが他方の関節に比べ悪ければ、上記日整会方式によりしっかりと可動域を測定していただくことが必要です。
4 ストレスレントゲン撮影
股関節・膝関節・足関節などの靭帯損傷では、関節にストレスをかけ関節の間隙を捉えるためにストレスレントゲン撮影が特に有意です。そこで、股・膝・足関節を受傷し、靭帯を損傷している可能性がある場合、ストレスレントゲン撮影を行っていただきましょう。
神経学的検査
各関節の靭帯・筋腱類に損傷が生じた場合、これを調べる検査があります。例えば、
◇肩関節:インピンジメントサイン、Painful arc sign Drop arm sign等
◇肘関節:内外反ストレステスト、後外側回旋不安定テスト、Tinel徴候(肘部管症候群等の神経異常のテスト)等
◇手関節:Finger extension test、Grind test等
◇股関節:Patrick test、ober test等
◇膝関節:前方引出しテスト、Lachman test、後方押出しテスト、Posterior sagging、
内外反ストレステスト、McMurry test等
なるべく早期に、各受傷部位に対応したこれら検査を施行いただいてください。
傷病別後遺障害等級認定の基礎知識と対策
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
東京海上日動火災保険㈱の不相当な治療費打切り理由について
-
韓国旅行中に交通事故に遭ったら
-
令和7年11月3日 韓国光州弁護士会・愛知県弁護士会共同セミナー講師を務めました。
-
東海交通遺児を励ます会の会報「はばたけ」100号記念号が発刊されました。
-
東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
-
右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
-
右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
-
三井住友海上火災の車両時価額の算定方法について~中古車販売価格の地域差を考慮に入れるべきでしょうか
-
東海交通遺児を励ます会の内河惠一先生へのインタビューに同行しました。
-
上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について