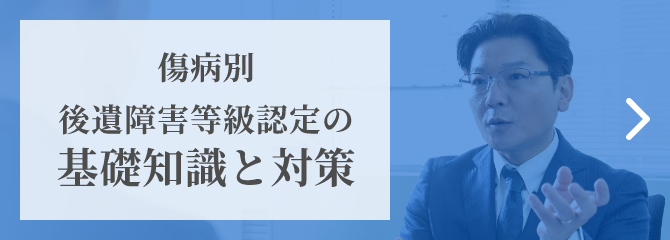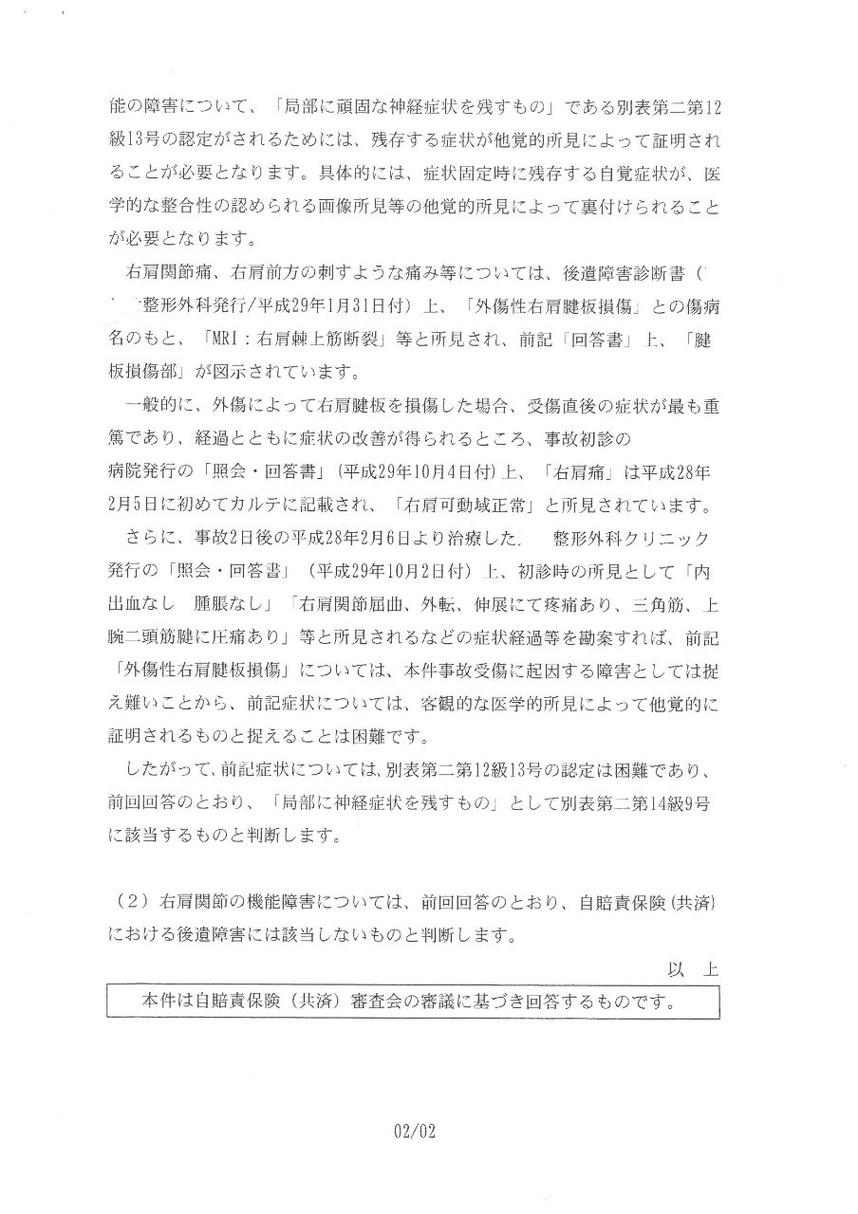後遺障害認定
受傷後相当期間経過後の症状の訴えについて
受傷当初からの症状の訴えがない、もしくは証拠上明らかにできない場合の問題点と対策
自賠責保険による後遺障害等級認定実務では、事故当初から当該部位に対応する症状の訴えがあることが必要とされますので、受傷後相当期間が経過した後に自覚された症状は、受傷当初からの症状の一貫・連続性が否定され、後遺障害該当性を否定されることが非常に多く発生しています。
また、受傷当初から症状が自覚されていても、当該部位の診断名が付されておらず、カルテにもその旨が記載されていなかったことにより、受傷当初からの症状の訴えが証拠上証明できない場合も多々あります。
自賠責で後遺障害が認められない場合、訴訟を提起し裁判所に後遺障害を認めてもらうことになりますが、損害の立証(証明)責任は被害者側にありますので、事故当初からの訴えが診断書やカルテなどの証拠上認められない場合、相手方から事故と後遺障害の因果関係が証明できないと反論され、裁判でも大きく争われます。
しかし、多様な症状が多発している事故直後から、被害者が一つ一つの症状を正確に医師に伝えることは困難ですし、医師もこれを一つ残らず、カルテに記録することも現実的ではありません。
事故当日は興奮状態だったので痛みを感じなかったが、翌日の朝痛みで目が覚めたなども良く見られます。
また、頭部や胸腹部に重傷を負った場合では、医師は救命措置を最も優先しますので、生命にかかわらないその他の症状を、事故当初から正確に診断し記録することも不可能です。
さらに、事故当初は裂創や打撲を負った部分の症状が強く自覚され、その症状が落ち着いてきたころ、当初は気付かなかった他の症状が明確に自覚されてきたという経過を辿ることも多く見られます(マスキング論)。
その他、入院中ベッドから起き上がれるようになって初めて症状に気付いた、歩き始めてから右足首が痛いことに気付いた、退院後自宅に帰ってから忘れっぽくなっていることに気付いた、退院して静かな環境で寝ようとしたら、耳鳴りがなっていることに気付いたなど、環境の変化によって症状を自覚することも良くお聞きします。
このように、賠償実務上は事故当初の症状の訴えが非常に重要視されるにも関らず、様々な理由から残存した症状が事故当初からしっかりと訴えられ、記録化されているとは限りません。
そのため、事故当初から症状が訴えられていなかったから、その旨がカルテ等の医証に記録されていなかったからといって、安易に残存症状と事故との因果関係を否定し、後遺障害等級認定を否定することはできないように思います。
そこで、このような事態に陥らないよう、以下の対応が求められます。
1 症状を自覚したらすぐに医師に訴えること
2 症状を自覚している部位の診断名が付されていなければ、すぐに診断名を付けてもらうこと
とはいっても、お忙しいお医者さんに沢山の部位に生じた症状をすべて正確に伝えることは難しいものですし、訴えたすべての症状がしっかりとカルテに記載されているとは限りません。
週末や祝日で病院がやっていないこともあります。
そこで、
3 発症部位と症状の内容とその程度をその都度自分で記録化すること
記録化といってもメモ書き程度で結構ですので、ご自身もしくはご家族により記録化しておいてください。
賠償実務では事故当初の自覚症状が重要視されますので、受傷当初はできれば毎日記載しておくことが重要です。
特に事故当初自覚していなかった症状を自覚した際は、後に発症日として重視されるので必ずその日は記載しておき、できれば、この時自覚した理由(歩き始めた、体重をかけた、家族からの指摘)も付記しておきましょう。
後でまとめて記載されたものより、その当時にその都度記載されたものの方が証拠価値は高くなりますので、記載した日も忘れずに付記しておいてください。
また、事後に改変しやすいパソコンやスマホなどのデータよりは、ノートなどに手書きしておいた方が信用性が高まります。
一方で、事故により症状が生じるということは、その前提として当該部位を受傷した(受傷機転)ということが必要です。
そこで、
4 受傷態様をできるだけ具体的に記録しておき、青あざや擦り傷、腫れなど受傷した痕跡が出来た場合は画像を撮影しておくこと
も非常に大切なことです。
また、お顔の傷などの醜状障害の場合、傷跡とシワやシミとわからなくなってしまうこともありますので、事故当初の傷跡の状況を撮影しておくことはとても重要です。
事故直後に痛みを感じない医学的な理由
半場道子医学博士によれば、最近の神経科学から、痛みを抑制して生命を護る脳の疼痛抑制機構が明らかになりました(医学書院発行「慢性痛のサイエンス」・p38~43)。
すなわち、「快の情動系」として知られる中脳辺縁ドパミン系は、「快」だけでなく「痛み」の制御も操り、快を受けた時に幸福感が得られるドパミンシステムは、生体が侵襲され痛みを感じた時にも機能を発揮し鎮痛をもたらすとのことです。
戦場や交通事故で生命が危機に晒されたときに、このドパミンシステムによる疼痛抑制が、瞬時にかつ過剰に機能し、さらには、この疼痛抑制は非常事態のときばかりでなく、日常的な些細な痛みの際にも機能しているとのことです。
我々法律家も「事故当初は興奮状態にあり、痛みを感じにくい状態であったため、事故直後は〇部の痛みを自覚していなかった。」と主張することがありますが、その論拠は経験則的な感覚的なものでに過ぎませんでした。
しかし、この「慢性期のサイエンス」の該当ページには、このドパミンシステムについて、神経回路系と脳内回路系から詳しくわかりやすく説明されていますので、上記事実主張を医学的に裏付けることが可能だと考えています。
また、自賠責調査事務所や加害者側弁護士などから症状の因果関係を否定する論拠として良く挙げられる「事故直後が症状が最も重篤で次第に軽快していく」との反論を崩すことが可能とも思われます。
マスキング理論に言及した判例
事故から約2週間経過後に初めて訴えた痺れ感について後遺障害を認めた判例(名古屋地裁平成28年2月26日判決)
事故から約2週間を経過して初めて右上肢のしびれ感を訴えた事案(自賠責非該当)で、名古屋地裁平成28年2月26日判決(自保ジャ1972号)は下記のとおり論じて、右上肢のしびれ感の後遺障害を認めましたが、その判旨は非常に参考になりますので以下引用します。
なお、弁護士丹羽は、本判決を下した伊藤隆裕裁判官につき、訴訟進行は厳し目ですが、通り一遍等の判断を決してせず、一つ一つの事例や問題点を丁寧に検討し、被害者側のみならず当事者双方にとって常識的な十分納得いく判断を示して下さる裁判官だと評価しています。
「また、原告は、左方からの入力であった本件事故により身体の左側に打撃を受けるとともに、反動により右半身を車体内部に打ち付け、事故直後はこれらによる疼痛が強かった旨供述しているところ、同供述は、受傷当初の医事記録等と矛盾しない。そして、このような疼痛の症状が、既に生じている痺れ感等の症状をマスキングしてしまうことはあり得ることであるから、受傷当初2週間程度、原告が上肢の痺れ感等の症状を訴えなかったことをもって、神経障害発生と本件事故との因果関係を否定することはできない。」
事故後2か月経過して訴えられた頚部痛について、事故との因果関係を認めた判例(名古屋地裁平成28年2月19日)
上の裁判例と同時期に伊藤裁判官によって下された名古屋地裁平成28年2月19日判決(交民集49.1.219)では、下記のとおり論じて、事故から2か月を経過後に初めて訴えられた頚部痛について、事故との因果関係が認められました。
「頸部痛の訴えが顕在化したのは、事故後約2か月経てからであるから、これが本件事故によるものか疑問の余地がないわけではない。しかし、本件事故直後の時期は、胸骨骨折及び多発的肋骨骨折による相当強い疼痛に苛まれた状態にあったことから、これに比べれば軽微である頸椎捻挫の疼痛を原告が認識しなかったとしても何ら不自然ではなく、上記骨折の疼痛が軽減するにしたがって、その背後に隠れていた他の疼痛が顕在化するということも、自然な経過であるといえる。」
なお、弁護士丹羽が獲得した、事故直後自覚し医師に訴えた症状が、カルテ等の医証上適正に記録されていなかったがために、自賠責で脊髄損傷が否定され14級9号に留まったものの、訴訟で脊髄損傷が認められた名古屋地裁平成30年4月18日判決をこちらで紹介しています。
後遺障害認定
- 高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
- 高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
- 東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
- 右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
- 右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
- 上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について
- 自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について
- むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
- 右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと
- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
-
高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
-
東京海上日動火災保険㈱の不相当な治療費打切り理由について
-
韓国旅行中に交通事故に遭ったら
-
令和7年11月3日 韓国光州弁護士会・愛知県弁護士会共同セミナー講師を務めました。
-
東海交通遺児を励ます会の会報「はばたけ」100号記念号が発刊されました。
-
東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
-
右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
-
右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
-
三井住友海上火災の車両時価額の算定方法について~中古車販売価格の地域差を考慮に入れるべきでしょうか