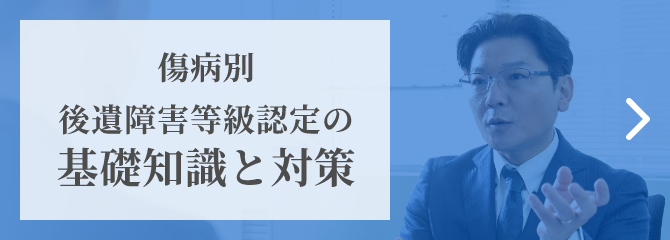後遺障害認定
脊柱変形(椎体圧迫骨折)の逸失利益の主張方法について(名古屋高裁令和5年9月29日判決に基づいて)
自賠責8級相当認定の腰椎圧迫骨折の被害者の主に逸失利益が争われていた事案につき、令和5年9月29日名古屋高等裁判所において判決が下されました(自保ジャNo.2163p47)。
結論としましては、原審認定どおり(控訴・附帯控訴いずれも棄却・確定)、後遺障害等級は8級相当が認められたものの、労働能力喪失率については事故後明らかな減収が生じていないことを踏まえて20%にとどまりましたが、控訴審では原審に引き続いて、脊椎圧迫骨折の逸失利益を論じる際に非常に先例性に富む判断を多数いただきましたので、かなり専門的な内容になりますが、今後の主張の参考にしていただきたく以下ご紹介いたします。
後遺障害等級について
争点
本件では腰椎椎体前方椎体高の圧壊の程度が50%を超えるとして、自賠責保険で後遺障害8級相当の認定を受けましたが、相手方は、レントゲン画像を再計測し50%を超えないとする医師の意見書を提出し、後遺障害等級11級7号に留まると主張しました。
これに対し当方は、A医師及び甲病院に所属するB医師他7名の整形外科専門医の先生に、レントゲン画像を再計測いただき、その平均値をもって圧壊率50%を超えることを主張しました。
控訴審の判断
『X線画像の特性や目視で行うX線画像の読影の性質上、測定者間での差異を減らして正確な数値を得るために、複数の医師による計測を実施して、その平均値を採用することが合理的であり、かつ、精度の高い測定と言える』
『レントゲン画像は、放射線を身体に透過させて立体物である骨を二次元の平面フィルム画像上に描出したものであり、放射線は奥へ行くほど広がりをもつ性質を有しているため、椎体の各頂点も手前側と奥側でそれぞれ4点が描出されるところ、・・・C医師(注:相手方医師)は前方椎体高を椎体の奥側で計測し、その結果他の医師の計測値よりも前方椎体高が大きい値になっていることが認められる』としてレントゲン画像の特殊性に触れたうえで、相手方の意見書の測定結果が乖離の大きい奥側の椎体高で測定されており、当方の8名の医師の測定結果と乖離する点を指摘し、相手方の意見書を排斥しました。
主張のポイント
圧迫骨折の後遺障害等級は前方椎体高の圧壊の程度(圧壊率)で判断され、その程度は医師が画像を見て手動で計測することになりますが、上記のとおりレントゲン画像は椎体の各頂点が取りづらいこともあり、また、対象椎体がX線源から離れるほど、椎体高は高くなりますので、用いるレントゲン画像によっても数値は異なることになり、検者によってその測定値に大きな差が生じます。
また、恣意的に乖離の大きい奥側の椎体高を測定することにより測定値を大きくすることもできます。
これを検者間格差といいますが、その格差を是正するためには、なるべく多くの医師に圧壊の程度を測定してもらいその平均値を出すことで、より圧壊率測定の精度を高めることができます。
後遺障害逸失利益について
争点
本件において相手方は、被害者の後遺障害逸失利益について、具体的な症状としては腰痛であり、これは神経症状にすぎないので14級相当であり、また事故後減収が生じていない以上、逸失利益は生じていないと主張しました。
脊柱の変形障害が後遺障害に当たるとされる理由
まず、控訴審は脊柱の変形障害が後遺障害に当たるとされる理由について以下のとおり判示しました。
この点は、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会「整形外科の障害認定に関する専門検討会」の平成16年2月報告書31頁以下のとおりです。
『脊柱の変形障害は、脊柱の支持機能・保持機能に影響を与え又は与えるおそれがあることにより労働能力に影響を与えると考えられることから後遺障害とされている』
脊柱の変形による発症の具体的機序
そして、本控訴審判決の注目点の一つとしては、以下の事実を認定し、脊柱の変形障害が各症状を生じる医学的なメカニズムを明らかにした点です。
これまで、脊柱の変形障害により腰痛や易疲労性、関節可動域制限が生じる原因を明らかにした一般的な医学文献や判決はなかなか見当たらず、賠償請求者側としても大変苦労していましたが、当事務所のHPで紹介した文献のほか(こちら)、本控訴審判決で脊椎専門医であるA及びB医師の意見書の内容を詳細に引用いただいたことで、今後、脊柱変形による発症についての具体的な主張が飛躍的に進んでいくことと考えられます。
『A医師は、脊柱は、椎体だけでなく椎間板・筋腱靭帯類等の周辺組織と一体となって支持されているところ、脊柱の変形が生じた場合、脊椎アライメントを正常に保つために他の脊柱や腰椎椎間関節、椎間板、筋腱靭帯類に過大な負担が生じ、腰椎症状や易疲労性を引き起こすと考えられ、加齢によりこれらの脊柱の支持機能が低下していけば、これらに伴い代償措置を失うことで後彎変形が進行し、腰痛や腰椎可動域制限の悪化、腰椎椎間板障害、変形性腰椎症等の発症を起こす可能性が高い旨の意見を述べている』
『B医師は、局所後彎を来すと脊柱筋が伸張し、脊柱筋内圧が高まり腰痛を来すこと、可動域低下が生じると椎間関節が拘縮・変化していき椎間関節由来の腰痛も生じるようになること、局所後彎が生じることで前傾姿勢が進行すると、上位脊椎負荷がかかり追加骨折を来すこともありうるとの意見を述べている』
将来的な症状の悪化について
本控訴審判決の注目すべき2点目は、以下のとおり、上記A及びB医師の意見書を基にして、圧迫骨折による症状の将来的な悪化の可能性について明示したうえで、これを労働能力喪失率の判断の要素とした点です。
『加齢により腰椎椎間関節、椎間板、筋腱靭帯類等の脊柱の支持機能が低下することに伴い、脊柱の変形の代償措置を失うことで後彎変形が進行し、腰痛や腰椎可動域制限の悪化、腰椎椎間板障害、変形性腰椎症等の発症を起こす可能性や局所後彎による前傾姿勢の進行による追加骨折の可能性が指摘されていることを踏まえると、被控訴人には将来的な症状の悪化が予想され』、『被控訴人の従事している業務の内容が相当程度腰部に負担がかかるものであることや将来の増悪の可能性からすれば、将来における収入の減少の蓋然性があるといわざるを得ない。』
主張のポイント
今後、圧迫骨折による労働能力喪失を論じる際には、上記のとおりの加齢による周辺軟部組織の代償措置の減少に伴う後弯変形の悪化による症状の増悪可能性を指摘したうえで、将来的な労働能力喪失の程度の悪化や減収の可能性についても必ず触れるべき点となります。
当事務所でも、従前より脊柱の圧迫骨折では将来的な症状の悪化に伴う労働能力の減少の可能性について取り上げており、近時の将来的な症状の悪化に触れた地裁裁判例を紹介していましたが(こちら)、今回、高裁でもその可能性が明らかに認められたことは、脊柱変形の逸失利益を巡る賠償実務に大きな影響を及ぼすものと考えられます。
少なくとも、将来的に労働能力喪失率を減少させる逓減法による認定は、本高裁判決の判断に反することになると弁護士丹羽は考えています。
減収が生じていない場合の逸失利益については、最高裁昭和56年12月22日第三小法廷判決の特段の事情(減収、昇進・昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、勤務先の規模・存続可能性等、本人の努力、勤務先の配慮等、生活上の支障等・中園浩一郎裁判官講演・赤い本2008年下巻9頁以下、田中敦裁判官同旨・判例タイムズ1346号18頁)により将来的な減収可能性を判断することが一般的ですが、圧迫骨折による脊柱変形は、この判断の枠組みにあてはめれば、より将来的な減収可能性が認められるべき障害類型であるとさえいえると思います。
各種手当の基礎収入性について
なお、本件では、相手方から、被害者に支給されていた各種手当(準夜手当、待機手当、住宅手当、職責手当)については労働能力に影響なく支給されるものであることから、逸失利益の基礎収入に含むべきでないとの主張がなされましたが、原審にひきつづき控訴審でも、個々の手当の性質を詳細かつ丁寧に認定し、いずれも将来的な減額・喪失の可能性があるとして基礎収入に含めました。
各種手当の基礎収入性についてはこれまで明確に争点化されておらず、詳細にふれた判例もほとんど見当たりませんが、今後、各種手当の基礎収入性について明示的に争われる可能性があり、本高裁判決はその大きな先例となるでしょう。
後遺障害認定
- 高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
- 高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
- 東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
- 右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
- 右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
- 上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について
- 自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について
- むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
- 右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと
- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
高次脳機能障害で辛い思いをされている方へ~S先生のご経験とメッセージ
-
高次脳機能障害を負った方への二次・三次被害について~ある自動車メーカーの対応
-
東京海上日動火災保険㈱の不相当な治療費打切り理由について
-
韓国旅行中に交通事故に遭ったら
-
令和7年11月3日 韓国光州弁護士会・愛知県弁護士会共同セミナー講師を務めました。
-
東海交通遺児を励ます会の会報「はばたけ」100号記念号が発刊されました。
-
東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について
-
右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介
-
右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介
-
三井住友海上火災の車両時価額の算定方法について~中古車販売価格の地域差を考慮に入れるべきでしょうか